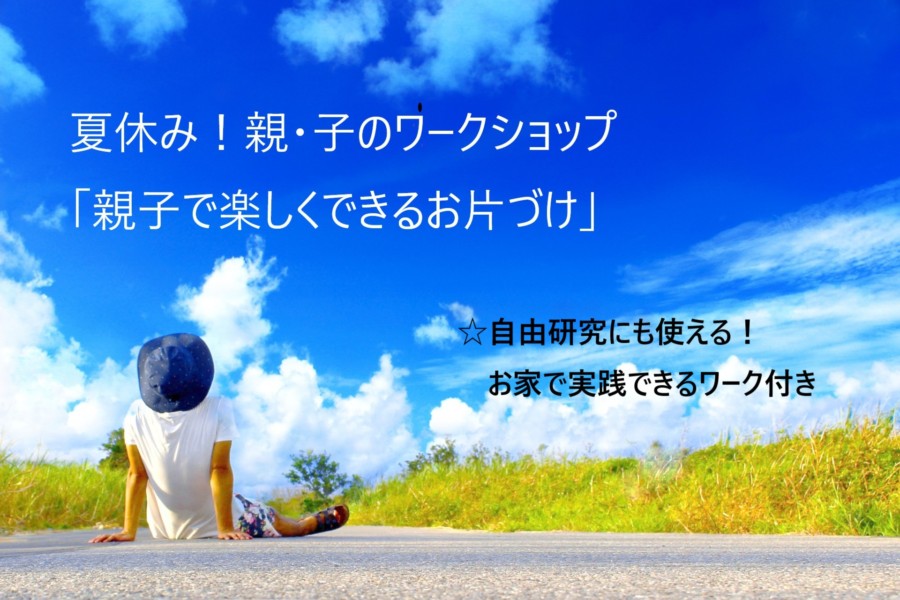石川県金沢市 整理収納アドバイザーの田中由美子です。
子どものおもちゃスペースに子どもの勉強机。
子どものクローゼットやその他子どもスペース。
親が子どものモノを片づけたほうが早いかもしれない。
でも、子どもに片付けを身につけてもらいたい。
子どもと一緒に整理をしたいけど
どういう手順で進めていけばいいの?
そんなお悩みを持っているお母さんへ
我が家では、子どもと一緒に文房具ボックスを整理しました。
ちなみに、文房具は無印良品のポリプロピレン収納ボックスに
収納しています。
今日は、子どもと一緒に整理をする手順についてお伝えしていきますね。
目次
整理の手順①収納からすべてのモノを出す
まず、子どものモノをすべて出すところから整理は始まります。
リビングの机の上でも床に新聞紙をひいてでもよいので、
片付けたいモノの中身を全部だしましょう。
子どもは集中力が続かないので、小さいスペースから始めることをおススメします。
ちなみに、我が家では子どもが全部並べていました。

整理の手順②要・不要の判断をする
子どものモノをすべて取り出したら次は、要・不要をする作業に入ります。
このモノは必要か?必要でないか?ということですが
要・不要の判断は子どもには分かりにくいので、
「今、使っている?」「今、使っていない?」と尋ね
使っているか、使っていないかで分けると良いです。
ちなみに我が子は、要る?要らない?と聞くと、必ず「わからん。」と返ってきます。
使っているか、使っていないかと事実を尋ねた方が、子どもにはわかりやすいですよ。
子どもは、迷いなく、使っているか、使っていないか分けていました。

整理の手順③わける
次に「わける」作業に入ります。
場所別や、使用目的別、アイテム別…色々分け方があります。
今回はアイテム別にえんぴつ、ペン、はさみやのり…をわけました。
几帳面な我が子。綺麗にわけていました。
性格が出ますね…。

整理の手順④使用頻度を確認する
最後は、アイテム別にわけたモノをさらに使用頻度でわけていきます。
整理の手順③までは親子一緒でも親だけでもできますが
この使用頻度の確認は使っている本人にしかできません。
「毎日使っている?」「あまり使わない?」「週に1回ぐらい使う?」
と、子どもが分かるような言葉を工夫して使用頻度の確認をしていきます。
実際、子どもに使用頻度の確認をしてみると…
私がイメージしていた使用頻度と子どもの判断が違うんですね。
色ペンはよく使うモノだと思っていましたが
子どもは「これはほとんど使わない。」と言っていました。
使っている本人しかわからないんだなーって実感です。

最終的に使用頻度で分けたモノをボックスに使いやすく戻して終了です。

まとめ
子どもと一緒に整理を進めていくときの手順をお伝えしましたが
いかがでしたでしょうか?
そういう我が家も気が付くといつもグチャグチャ…
定期的な見直しが必要です。
お片付けは毎日の積み重ねなので
子どもに片づけを身につけてもらい!と思うのであれば
まず親である私たちがしっかりと片付けについて学ぶことが大切ですね。